植物だってストレス社会!? 〜環境ストレスとその知恵を学ぶ〜
2025年7月10日(木)晴れのち雷雨
本日は座学の日。朝は気持ちのよい青空が広がり、「今日も暑くなりそうだな」と思いましたが
天気予報の通り、午後には空がゴロゴロと鳴り始め、夕方にはすっかり暗くなって、大粒の雨がザーッと降り出しました。
まさに“夏の空模様”という一日でした。
本日の1限目の講義は「植物生理」。テーマは【環境ストレス】です。
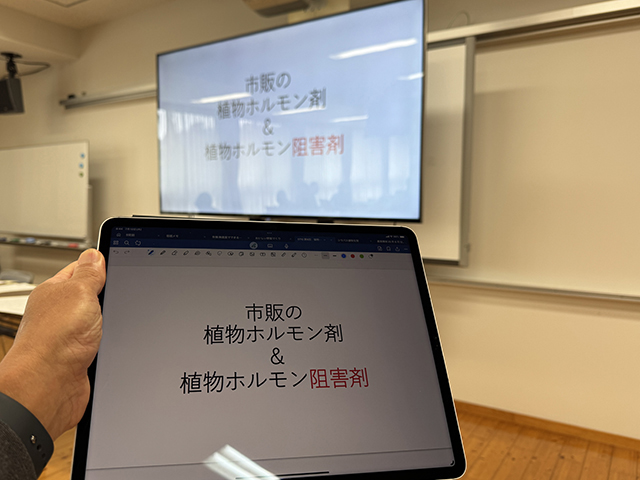
教室に入り、スライドとiPadに映し出された「市販の植物ホルモン剤&阻害剤」の文字を見て、「おっ、有機農業でもいろいろ勉強しておかないとな…」と気を引き締めていたのですが、実際には市販のホルモン剤の話はサラッと紹介されただけで、本題はそのあと。
メインは“植物と環境ストレスの戦い”についてでした。
私たち人間が暑さや乾燥に悩まされるように、植物もまたさまざまな外的ストレスと日々向き合っています。
今回は、そのストレスに植物がどんな風に立ち向かっているのかを学びました。
たとえば──
- 🌡 高温ストレス:葉から水分を出して温度を下げる「蒸散」や、熱で壊れそうな酵素やタンパク質を守る「ヒートショックタンパク質(HSP)」の合成。
- 🌵 乾燥ストレス:葉や茎の毛のような構造「トライコーム」や葉針で水分の蒸発を抑える工夫。
- 🧂 塩ストレス:余分な塩分を液胞にためて隔離したり、古い葉に集めて落葉させることで被害を最小限に。
- 🌞 強光ストレス:過剰な光エネルギーを熱に変えて逃がしたり、活性酸素を消去してダメージを防ぐシステム。
- 🌊 低酸素ストレス:冠水時に根の酸素不足を補うために「通気組織(空洞)」をつくって酸素を確保。
- 🦠 病原体ストレス:感染した部分の細胞を“あえて”死なせて拡散を防ぎ、「ファイトアレキシン」という抗菌物質を合成。
そして何より驚いたのは、植物は言葉こそ話せませんが、「メチルサリチル酸」という揮発性の物質を使って、他の葉やまわりの植物に“病原体に注意!”と警告を送るということ。
植物たちは静かに、しかししっかりと情報を伝え合いながら生きているんですね。
中でも興味深かったのが、イチゴにお湯をかけるという“熱ショック療法”。60℃のお湯を週1回かけることで病気への抵抗力が高まり、農薬の使用量を1/3に減らせたという話には、「なるほど、植物の生命力ってすごいな」と感心しきりでした。
植物たちは、私たちが思っている以上にしたたかで、そして繊細。
今日の講義を通して、声なき声で懸命に生きる植物たちの世界があることを学びました。

