農業は管理だけじゃない、持続可能性まで含めて・・GAP概論
2025年10月2日(木)晴れ
本日は座学で「GAP概論」の講義を受けました。
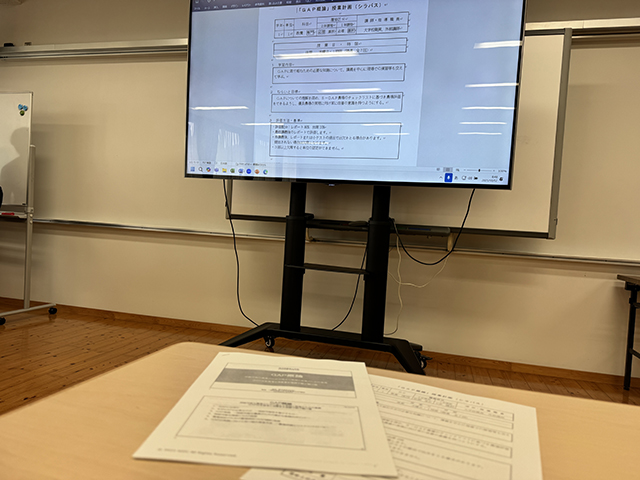
まず心に残ったのは、「生産性」と「健全性」の両立という視点です。
目先の収量や効率を意味する「生産性」と、環境保全や安全確保といった長期的な持続可能性を意味する「健全性」。
これらは時に相反する要素ですが、そのバランスを取ることが現代農業には欠かせないと先生が強調していたのが印象的でした。
もう一つは、日本のGAPの定義の狭さです。
日本では「農業生産工程管理」と訳されていますが、これだと“工程管理”の側面に偏ってしまうとのこと。
本来のGAPは、環境や社会、働く人までも含めて“持続可能性への配慮”を求める広い概念。
単なる「工程を管理しましょう」という話ではなく、農業全体を持続可能にしていくことこそ本質だと理解しました。
さらに、講義では現代農業が直面するリスクについて、数字をあげてイメージしやすいお話しがありました。
日本の畑地由来の地下水の約60%が飲用不適合であること
残留農薬は25mプールにスプーン1杯(3〜5g)で基準超過となるほど厳格であること
農業の死亡事故率は他産業の約10倍に達し、唯一増加傾向にあること
そして、国内のGAP認証取得率は1%未満にとどまっていること
どれも強烈な現実を突きつけられる数字ばかりで、農業の重みを実感する一日となりました。
今日の学びを通して、就農後に必要なのは「栽培の技術」だけでなく、「計画と管理を通じてリスクを減らす姿勢」も
大事だと改めて感じています。

